今、日本の大学から生まれるディープテック・スタートアップが、国策の主役として大きな注目を浴びている。政府が掲げた「スタートアップ育成5か年計画」を追い風に、かつてない規模の資金が大学発の革新的な技術へと流れ込み、起業件数は過去最高を記録。一見すると、日本のイノベーションエコシステムは順風満帆な航海を続けているかのように見える。しかし、その華やかな舞台裏では、深刻な問題が静かに進行している。潤沢な資金が供給される一方で、多くの有望な技術が製品やサービスとして顧客の元に届くことなく、成長の壁に突き当たっているのだ。これは単なる「資金ショート」ではない。より根深く、構造的な課題である「顧客ショート」——つまり、買い手の世界に製品が存在しないという事態が多発している。本稿では、この熱狂の陰に潜む歪みを多角的に分析し、日本のディープテックが真に社会実装を成し遂げ、未来を切り拓くための処方箋を提示する。
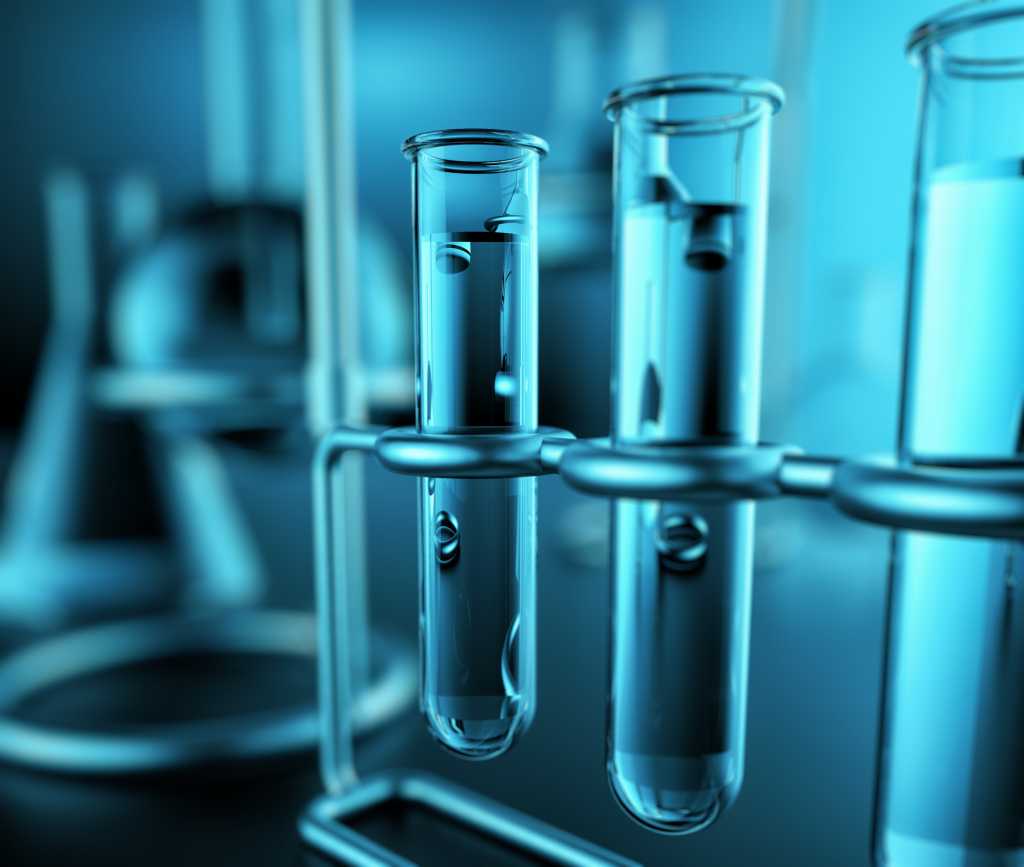
国策が生んだブームの光と影
2022年11月に政府が決定した「スタートアップ育成5か年計画」は、人材育成、資金供給、そしてオープンイノベーションの促進という三つの柱を掲げ、創業から成長までを切れ目なく支援するこの計画である。大学発スタートアップは極めて重要な役割を担う存在として位置づけられた。経済産業省の調査によれば、2024年10月時点での大学発ベンチャーは5,074社に達し、前年から786社も増加するという過去最高の伸びを記録した。まさに、大学発スタートアップは「数の時代」を迎え、エコシステムの裾野は確実に広がりを見せている。
ディープテックスタートアップにはかなりの補助金が流れている。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が展開する「ディープテック・スタートアップ支援事業(DTSU)」や、GX(グリーン・トランスフォーメーション)関連の支援枠は、研究開発段階から試作品の製作、さらには量産化実証まで、事業の成長フェーズに応じて段階的かつ手厚い支援を提供し、その規模感は破格と言える。また、科学技術振興機構(JST)の「大学発新産業創出基金事業」も、令和4年度の補正予算で988億円という巨額の基金を造成し、大学発スタートアップの創出から事業化までの伴走支援体制を少なくとも資金面では手厚くしている。
長期的な視点と高い不確実性を伴うディープテック開発において、こうした公的資金の存在は不可欠であり、エコシステムを支える生命線であることは間違いない。問題は、もはや「資金がない」ことではない。真の問題は、「潤沢に供給される資金が、顧客の意思決定という最終ゴールにまで正しく繋がっていない」ことにある。多くの助成金は、技術の新規性や優位性を証明する研究開発フェーズに重点的に投下される。しかし、その技術を搭載した製品が、実際に顧客である企業のどの部署で、どのような稟議プロセスを経て、いかなる予算で購入されるのか。その後の運用や保守は誰が責任を負うのか。こうしたビジネスの現場で繰り広げられるリアルな現実と、研究開発の現場との間には、深い断絶が存在する。資金の流れが、顧客が実際に購入を決定する「意思決定線」と噛み合っていないため、多額の公的資金が投じられたにもかかわらず、技術は研究室や実証実験の場から一歩も外に出られないという悲劇が繰り返されているのだ。
最も深刻な病、「顧客ショート」の実態
成長途上のスタートアップが直面する困難として、一般的には「資金ショート」が知られている。しかし、現在の大学発ディープテックが直面しているより深刻な病は、「顧客ショート」と呼ぶべきものだ。これは、運転資金が枯渇する前に、自社の製品やサービスを購入してくれるはずの顧客が、その世界線に存在しないという事態を指す。技術的には極めて優れており、実証実験も成功裏に終えた。しかし、いざ販売しようとすると、誰も買ってくれない。なぜなら、その製品は顧客が抱える本当の課題を解決するものではなく、あるいは、導入に伴う様々な障壁が全く考慮されていないからだ。
ディープテックが、革新的な技術シーズを起点に始まることは避けられない側面がある。しかし、シーズ起点であることが顧客不在の免罪符になるわけではない。経済産業省が発行した『ディープテックスタートアップの評価・連携の手引き』では、事業会社との連携を通じて、品質保証、業界規格への適合、販路の確保、保守体制の構築といった、事業を10から100へと成長させるために不可欠な要素を埋めていく必要性が明確に指摘されている。これは、政策当局自身が「PMFまでの道のりは険しく、顧客への導入を現実的に設計することが成功の鍵である」と認識していることの証左に他ならない。
しかし、現場で起きている現実は厳しい。例えば、画期的なAI医療診断システムを開発したスタートアップを想像してみよう。技術の精度は既存の製品を凌駕し、論文もトップジャーナルに掲載された。しかし、いざ病院に導入しようとした時、途方もない壁が立ちはだかる。病院の複雑な電子カルテシステムとの連携はどうするのか。個人情報保護法や医療機器としての薬事承認はクリアできるのか。万が一の誤作動やシステムダウン時の責任分界と保守体制は誰が担保するのか。そして何より、現場の医師や技師が日々の業務の中で抱える、既存のワークフローを変更することへの抵抗感や、導入によって大して収益が増えるわけでもないのにかかってしまう莫大なスイッチングコストをどう乗り越えるのか。こうした「顧客の地図」——導入先の稟議ルート、規制や安全審査のプロセス、既存ベンダーとの力関係、運用・保守の負荷といった、生々しい現実を詳細に描き込めていない事例が後を絶たない。その結果、開発は順調でも、製品は買い手の世界に存在しない幻のまま終わり、「資金ショート」ではないのに成長が止まるという、最も避けたい結末を迎えてしまうのである。
研究者を起業へと駆り立てる構造
では、なぜこのような「顧客ショート」が多発するのか。その根源を探ると、研究者が置かれている厳しい環境に行き着く。日本の科学研究を支える競争的資金の代表格である科学研究費助成事業(科研費)は、近年、新規採択率が3割を切る厳しい状況が続いている。2024年度は29.1%、2025年度も28.8%と、多くの優れた研究提案が予算の制約で採択されないという現実がある。さらに、国立大学の基盤的な経営を支える運営費交付金も、2004年度以降、減少傾向が続いており、研究室の安定的な運営は年々困難になっている。
このような構造的な問題は、研究者たちに深刻な影響を与えている。研究の継続性や、若手研究者や技術スタッフの雇用を維持するため、彼らは常に新たな資金源を探し求めなければならない。こうした状況下で、政府が手厚い資金を用意する「スタートアップの起業」が、魅力的な選択肢として浮上してきたのだ。もちろん、すべての研究者が不純な動機で起業しているわけでは決してない。しかし、制度や資金の組み合わせが、結果として「起業が研究資金を補完する」という側面を機能させてしまっている事実は否定できない。これは、個々の研究者の倫理観を問う問題というよりも、現在の制度が生み出すインセンティブ(誘因)がもたらした、構造的な歪みと捉えるべきだろう。加えて、大学教員の兼業やクロスアポイントメント制度に関するガイドラインが整備され、利益相反マネジメントを前提とすれば、研究者がスタートアップに関与しやすくなったことも、この流れを後押ししている。もはや、「関与できないから非公式に」という時代ではなく、「適切に管理して関与する」というオープンな時代に入ったことで、起業という選択肢はより身近なものになったのだ。
顧客側の視点に立った評価が必要か?
巨額の公的資金を配分する資金配分機関は、その評価軸を見直す必要があるかもしれない。技術の新規性や独自性といった、従来の評価基準に偏重する姿勢を改め、顧客側の意思決定プロセスを具体的に描き出した「需要の設計図」の提出を、申請の必須要件とすることが有効となるだろう。具体的には、導入を想定する現場でどのようなKPI(重要業績評価指標)が重視されているのか、導入後の責任分界点はどこにあるのか、必要となる業界規格や規制、認証、さらには保険償還への道筋はどうなっているのか。既存システムとの統合計画や、運用・保守(O&M)の担い手と費用負担、そしてスイッチングコストを誰がどのように負担するのかまで、一次情報に基づいて詳細に記述させることが望ましいだろう。
日本の大学発ディープテックを取り巻く環境は、今、大きな転換点を迎えている。政府の強力な後押しにより、資金の流れは確保され、創業件数も過去最高を記録した。エコシステムの裾野は広がり、量的な基盤は整ったと言える。だからこそ、今問われるべき次の論点は、「その豊富な資金が、顧客の意思決定線という最後の砦にまで届く設計になっているか」という、質的な問題である。








